当サイトで
◆ 2050年社会政策ビジョンにおける教育制度改革考察・提案のための参考図書(2021/10/13)
という記事を投稿して既に2週間近く経ちました。
<国土・資源政策><社会政策><経済政策><国政政策>と4つの領域に分けて、2050年の望ましい社会創造に向けてのさまざまな考察・提案に継続的に取り組んでいく。
こう考えている中、教育問題への取り組みがなかなか進まず、なんとかきっかけを作り、シリーズ化をと考えての手元にある参考図書整理作業だったのですが、勢いがつかないというか、グズグズしているというか。

教育政策、教育制度改革を論じる前に感じる弱音
中国、韓国、北朝鮮の思想教育の脅威・恐怖を考えれば、国としての教育方針の重要さは言うまでもない。
しかし、教育勅語の時代に引き戻すベクトルが強い自民党保守層を考えると、単純に教育制度改革の必要性を喧伝することには神経を使うべきことも同様だ。
コロナ禍で一気にクローズアップされた、オンライン教育を始めとするICT教育、教育DX、EdTechは、教育改革の象徴的な課題と位置付けられるが、単純に技術的な課題としてではなく、家族・世帯格差や地域間格差、担当する教員の能力問題、そして最も基本の部分での、教育ソフトの企業・民間への移行・依存度の傾斜への不安・不信も見逃してはいけない。
小学校から行われるようになって久しい英語教育が、これまでどの程度の成果・効果を上げつつあるのか、英語だけが国際的な人材育成に必要な言語というわけではないが、やはり、その取り組みに明確な成果が生まれつつあることを確認したい気持ちは強い。
英語教育はほんの一例だが、中室牧子氏や松岡亮氏が強く主張する、教育制度等領域における「EBPM」、「データと研究に基づく政策立案」の必要性・重要性は、十分理解できる。
しかし、この問題は、教育に限らず、日本の政治・行政に通底する課題であり、なんとなく、プラン・ドゥー・チェック・アクションという単純なマネジメント・サイクル表現を口にすればそれで通ってしまうようになっている風潮を根本的に改める必要がある。
そうした認識をもつ政治家や政党が存在しないことは、現在終盤を迎えつつある衆議院選挙における各党・各候補者の政策・公約を見聞きし、こうした選挙が繰り返し行われていることを考えればわかることだ。
エビデンスの必要性の主張の際に、個人の経験に基づく、あるいは伝統に委ねる教育に対する考え方や主張・偏見・独断などが批判されるが、それを極力戒めようと意識しつつも、やはり私自身の経験に基づく教育についての考え方はそれなりにある。
団塊の世代の最終年齢に引っかかる者だが、正直なところ、良い意味で影響を受けた教師・教員はいない。
担任であったり、個別の授業を受けた教師・教員の教育者として資質・適性・能力、専門分野の講師としての評価・感想などを思い起こしてみても、教師・教員という職種・職業に携わる人々という捉え方でとどまる。
また別の観点からだが、同じ義務教育と高校教育を受けた同級生の就職先などを少ない情報で辿ると、私立大学出身者の多くが地元に戻り、何人かが市役所など地方公務員などになっている。
なるほどこうやって社会は回っていくのか、と一つの典型を見た感がするのだが、それも教育のもたらしたものと思う。
私が考える学校教育の役割・使命、雑感・メモ
私自身が考える教育の役割・使命とは、一人の人間が、自分の意志・意欲・興味関心等に拠って、生き方・働き方を考え、選択し、実行・実現していく上での機会と情報、技術・技能などを提供するものと言えようか。
インスピレーションの枠でのことだが。
とは言っても、では自分のこれまでを振り返ると、その間に、生き方・働き方を明確に探し得たわけでは決してなく、社会人・企業人になり、その活動をする中で見出し、決定づけることができたものだ。
ということで、教育の意味・意義は、人によりけり、と言えるものだろう。
期待しすぎてもいけないし、期待が低すぎて、放任・放漫であっては無論いけないことは言うまでもない。
すなわち、学校教育での経験とは別に、企業人・組織人としての経験と、経営コンサルタントになってからの(人事制度設計・運用、業務改善・業務システム作り、人材育成等)経験を混ぜ合わせてみると、学校教育がすべてではないということができる。
そういう意味で、企業内教育も重要だし、その間の個人個人の意欲・姿勢も関係してくる。
これは、教育政策・教育制度改革を論じる領域とは異なる課題と言えるだろう。
この視点での経験や考えについては、ずーっと後になるかもしれないが、いずれ記事を書く機会を持つことができればと思っている。
ということで、学校教育で一人ひとりの生き方・働き方の一生が決まるわけではないということで、学校教育は、そうした準備機能の多くを担っているとも言えるわけだ。
そのために、どういう教育の在り方が望ましいか。
教育制度改革にはそういう視点も必要と思う。
今良く言われるようになってきている、「リスキリング」「リカレント」もその中の一つのテーマになるのかもしれないが、どうもその傾向には、個人個人への自己責任にまたもや導かんとする何らかの意志・意図そして糸が見え隠れしているような気がして、どうも面白くない。
(参考)
⇒ 高校教育の多様化を教育の水平的多様性実現の起点に:『教育は何を評価してきたのか』から考える (2020/6/26)

多面・多義的「教育格差」問題にどうアプローチするか
今回のツラツラの思いの最後に「教育格差」について。
一口で「教育格差」と言っても、その要素・要因の多様性・多義性を考えると、やはり一筋ならではの感がある。
家族・家庭(環境)格差(収入格差、両親・片親格差、親の学歴格差)、子どもの貧困格差、学校・教室格差、地域間格差、教育機会格差、IT基盤格差、ジェンダー差、国籍・外国人という違い、教師・教員差 etc.
これらが、それぞれ個々に課題と設定できるが、実はそれぞれが関連しあっているというのが実のところだ。
それだけに、先の主張は分かるが、EBPMの導入・利活用の困難さを一層感じさせられるわけだ。
そしてそこに、当然ながら、個々人の潜在的能力・適性や一人ひとりの関心先とその度合、意欲の違いなどが絡む、学生と教師・教員双方の。
そこに果たしてどのようにEMBPを持ち込むか。
無論、専門学者ではない私がEMBP云々を論じる資格も能力も持ち合わせていないのだから、考察・問題提起には、説得力や合理性が欠落することは明らかだ。
しかし、専門外の者としての言いようにも、少しばかりの合理性や納得度を加えることくらいの意義は持たせることができる気もする。
迷いつつも、その作業、教育格差問題に取り組んでいきたい。
そうこう思いつつ・・・。
教育岩盤を崩すよりも簡単な、当問題への考察・提起作業へ
さて、手元には、先日愛知県で問題になった、小学校で利用するPC端末に多数の不具合が出た事件?を一面で取り扱った中日新聞の記事があります。
原因は、指定された納入業者のずさんな製品選定と検査体制にあるとのことだった。
この問題は、先述書『教育論の新常識』「Ⅲ 教育政策は「凡庸な思いつき」でできている」の中の<EdTech: GIGAスクールに子どもたちの未来は託せるか>で扱われているGIGAスクール構想と関係がありました。
また、一昨日2021年10月25日と26日両日、日経一面で「教育岩盤」という特集記事が掲載。
・<変化を嫌う(1) 多様性求め異議相次ぐ 入試筆記なしの先端エンジニア大学、改善拒む旧弊打破>
・<変化を嫌う(2)黒板と紙を「信仰」 デジタル社会に追いつくか>
という見出しのものでした。
大学入試問題や9月入学問題、EdTech・ICT教育問題などを例に取り上げ、改革が進まない教育現場と政策の状況を「岩盤」と見て教育改革を強く促す内容となっています。
ということで、そろそろ気合を入れて、当サイトで提示している「教育政策2050年ビジョン」の各項の見直しも並行して進めていくことを想定して、個別の課題についての考察に取り組みたいと思います。
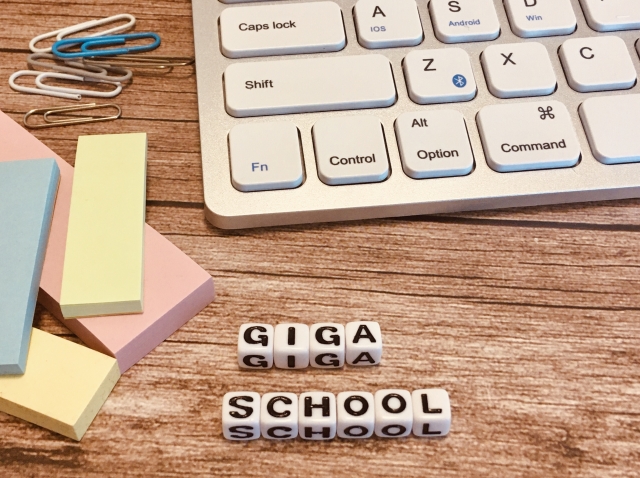
(参考)社会政策2050年ビジョンにおける<教育制度改革>個別重点課題;2021年10月現在
3.教育制度改革
(基本方針)
次世代を形成する児童・学生への期待は、教育機会の平等、教育格差の是正、学校や教育システムなどのインフラを経済的な不安なしで利用できる制度など、社会的共通資本としての教育制度・教育政策基盤が整備され、提供されて初めて、積極的な行動を求めることができるものです。
そのために必要なさまざまな制度の体系と方法を再構築し、自身の希望に挑戦し困難を克服する姿勢・能力・技術の向上や自己実現・社会貢献に結びつく多様な個性・人間性そして人生の実現の支援政策を推進します。
(個別重点政策)
3-1 義務教育改革(幼児教育・小学校教育・中学校教育)
1)5歳児・4歳児義務保育制導入
2)教育格差、いじめ・自死、学童保育等社会問題対策
3)新教育基本法改正、教科・教育方法改訂、Edtec活用システム開発
4)教員支援・教員養成支援
3-2 高等学校・専門専修学校教育改革
1)高等教育改革(受験システム、高校専門教育課程・専門高校多様化拡充)、専門専修学校教育改革
2)起業・経営専門スキル、IT・AIスキル教育課程拡充
3)学生交流・交換留学等教育国際化推進
4)ベーシック・ペンション学生等基礎年金、特別供与奨学金制度による経済的支援
3-3 大学・大学院教育改革、留学・社会人教育、生涯教育基盤拡充
1)大学・大学院教育改革、同受験システム改革、大学・大学院組織改革、研究者支援システム改革
2)学生支援制度拡充、特別奨学金制度、留学生支援制度
3)社会人キャリア開発・高度専門スキル開発教育支援、生涯学習基盤整備拡充
4)大学・大学院組織改革、高度教育技術システム開発
⇒ 社会政策2050年ビジョン
⇒ 2050年社会政策ビジョンにおける教育制度改革考察・提案のための参考図書(2021/10/13)
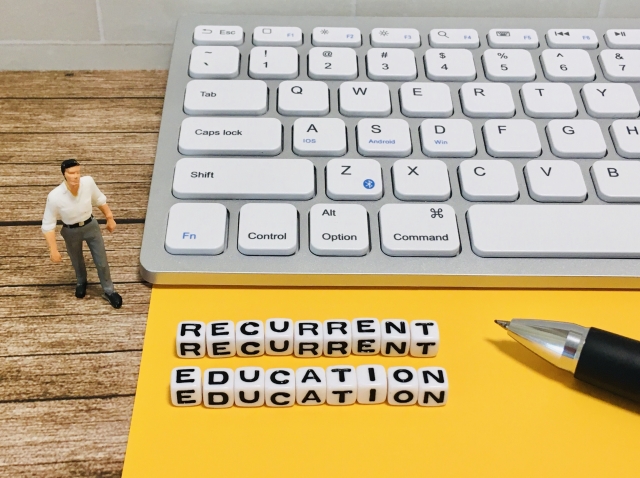
コメント