一昨日2022年1月21日付日経紙で、エネルギー関連記事を拾ってみたのが以下。
1.(真相深層)欧州が狙う「水素覇権」 早期量産へ大型投資 原発回帰で温暖化ガス実質ゼロへ
2.再生エネ電力 熱に変え貯蔵 コスト、電池の5分の1 シーメンス系や米新興が脱炭素促す
3.蓄熱市場、世界で1兆円 26年、出力調整の役割期待
4.関202電など3社、料金上限に 3月、燃料費転嫁できず 続く高騰で家計にも負担
5.発電所やガス設備検査、立ち会い・目視の規制を緩和 AIやドローン活用、担い手不足に対応
6.(エコノミスト360°視点)エネルギーコストの上昇抑制を 小山堅 日本エネルギー経済研究所専務理事
前回、その記事リストの1から3までを(海外動向編)として
グリーン水素と蓄熱発電:エネルギーをめぐる2022/1/21日経記事から考える長期エネルギー政策ビジョン-1(海外動向編)(2022/1/21)
という記事を投稿しました。
今回は残りの3記事を(国内動向編)として、概括します。

長期化するコロナ禍による燃料費高騰で、電力各社電力料金値上げ圧力強まる?
前回の3つの記事に続いて4つ目の記事は、以下。
「関電など3社、料金上限に 3月、燃料費転嫁できず 続く高騰で家計にも負担」
2016年の電力自由化以降、実際には下がるどころか、再生可能エネルギーの固定買い上げ価格制度により、電力料金に特別加算されて高い電力を使わざるをえなくなっているのが実態の日本の電力・エネルギー政策。
現在の電気料金はその2016年の電力自由化以降で最高値圏にあり、重い家計負担を負わされている状況だ。
コストダウンが可能になるレベルでの再生エネへの転換が簡単に進むはずはないのは当然予想されたこと。
そこへ長引くコロナ禍。
液化天然ガスや石炭などの燃料輸入価格の高騰が、火力発電に依存する大手電力を直撃。
一応、消費者が負担する電力料金には、燃料費上昇によるコスト増下においても、転嫁できる上限があるとのことだ。
しかし電力大手10社中3社がその上限に達しており料金転嫁は不能。
あとは自社の経営を直撃し、圧迫することになると報じている。
各電力大手の価格の設定基準: 「燃料費調整制度(燃調)」 と基準価格
電力会社は「燃料費調整制度(燃調)」によって事前に電源構成などから設定した基準価格と、足元の燃料価格の差額を電気料金に自動で転嫁できるという制度があるとのことだ。
従い、各社設定の「電源構成」の違いで、基準価格が異なり、高騰する燃料費を値上げに転嫁できる上限額とそれによる可能な上げ幅も、電力会社ごとに違うわけだ。
そこに攻勢を強めたい「新電力」が値下げ圧力をかけ、値上げ可能な条件にあっても簡単に値上げできない、しない状況が、消費者にとってプラスになるという予想もありうる。
が、新電力が、大きく日本の電力・エネルギーインフラを改革するには程遠い状況あることも現実であり、長期的に好転する見通しをえる可能性は少ない。
大手電力の気持ちを日経が代弁?
燃料高が長く続けば、いずれ他の7社においても上限価格までの値上げは止められず、現状の法律を変えて、歯止めとなっている条件を変更するよう政府に圧力をかけることになるのでは、と勘ぐってしまいます。
この記事で、随分細かく各大手電力ごとの基準価格や上限額までの余力などを事細かく調べて報じていることが、そうした大手電力の、値上げしたい気持ちと実情を代弁しているように感じられるゆえ、です。
電力行政、電源攻勢のからみでは、日経は、原発維持・積極活用論を主張している立場で、電力大手との強い結びつきを事あるごとに感じているのです。
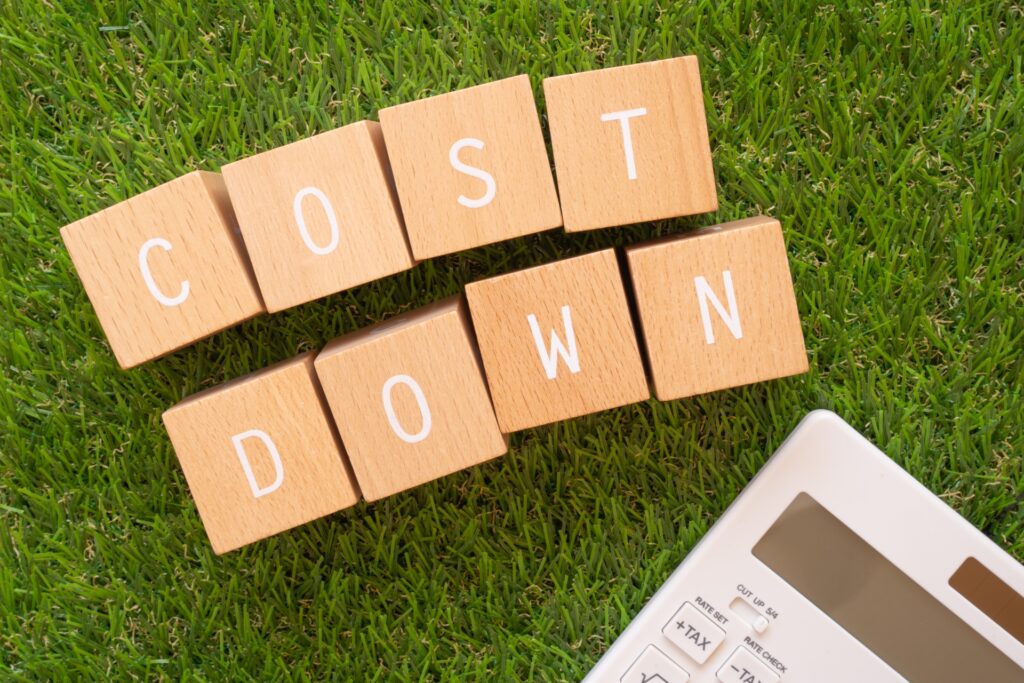
発電所・ガス設備等のアナログ的法定検査、規制緩和へ
次の記事は、
「発電所やガス設備検査、立ち会い・目視の規制を緩和 AIやドローン活用、担い手不足に対応」
というタイトルの記事。
地震や自然災害による電柱の倒壊や停電などの復旧作業は、人力に委ねざるを得ないことは、そうした被災状況と復旧作業や状況などの報道を見るたびに、やむを得ないこと、必要不可欠なことと理解納得し、頭が下がることが常です。
電力・エネルギー事業そのものは、DXデジタルトランスフォーメーションをイメージする感が強いですが、そうした報道からは、エセンシャル・ワークの代表とも感じることもあります。
その業界において、検針作業のリモート化などは、すぐにでも置き換えられると思いますが、非常に重要な、発電所やガス製造設備等の検査も、やはり人の手間をかけざるをえない作業。
というか、これまでは、安全性確保を理由にそうした規制をかけてきたわけです。
その立会い検査を必須とした規制を、まさに、ドローンやAI等DX化を図ることで緩和することを経産省が進めるというものです。
対象となる施設等は、原子力発電所は含まず、火力発電所、送配電設備、ガス製造設備、石油精製プラントなど。
併せて、再生可能エネルギー発電所の新設や保安を監督する要員緩和に関する運用ルールを見直すとあります。
改正が予定される関連する法律は、電気事業法とガス事業法、高圧ガス保安法など。
ただこの規制緩和が、担当者の高齢化対応やコストダウンの視点からのものでは本末転倒。
現状の施設の検査基準の緩和では当然なく、DX等の利用で、安全性が一層高まる、保証されるレベル・内容が必要とされるのは当然です。
従い、万一老朽化した施設を更新する場合は、より安全性を高める検査システムが組み込まれた施設・設備の開発・設置が必要であり、新設のものについては、当然のことです、
日本のこうした施設・設備の保安・維持検査には、高度な知識と技術が必要な公的専門資格を持つ技能職配置を必須としていたわけです。
低生産性を嘆く行政が、一方で保守的な姿勢を貫き通してきた背景には、実は関連業界等、何らかの利権がからむことがあったことも違いありません。
従い、多くの規制緩和は、これまでの利権構図を打ち破ることも同時に行われるはずですが、間違っても新たな利権構造が創出されることなどないようにと思います。
こうした観点からの論述部分はまったくないこの記事。
古いインフラ設備が増えて点検や保安の重要性が高まる一方、少子高齢化で働き手の確保は難しさを増している。
人材不足からおぼつかなくなるといった事態をデジタルで補完する。
危険が伴う業務や検査分野でデジタル化が進めば社員の安全確保にもつながる。
保安へのデジタル技術の導入は省人化の面で重要だ。
こうしたまとめで終わる記事には、それだけの問題じゃないでしょ、とひとこと添えたくなるのは、意地が悪いでしょうか?
DX化、IT化により、現状の検査業務システム改革、専門技術者の必要性や要件などの制度改革など多くの改革課題が発生しつつあるわけで、法改正にとどまるものでは決してない、長期計画を要するものですから。
もう一つ突っ込むと、これは規制緩和・規制改革ではなく、新たな基準・システム作りのための制度改革と呼ぶべき取り組みであると。

エネルギーコスト上昇要因の多様化にどう対応するか
6つの記事の最後に、専門エコノミストの以下の小論を持ってきました。
「(エコノミスト360°視点)エネルギーコストの上昇抑制を 小山堅 日本エネルギー経済研究所専務理事」
その基調とするテーマは、まさに「エネルギーコスト」抑制とそのための「エネルギーの安定供給」です。
2021年の前半、エネルギー問題に関する世界の話題は「カーボンニュートラル」「脱炭素化」一色に染まっていた。
しかし後半には原油、天然ガス、液化天然ガス、石炭、電力の価格が世界で同時多発的に高騰し、世界の関心を集めた。
エネルギーは私たちの生活や経済活動に必要不可欠だ。
その価格が低廉で安定している時には水や空気のような存在だが、ひとたび価格が高騰すると、一気に重要な政治・経済・社会問題になる。
この認識から始まり、こう展開します。
柔軟で強靭な(エネルギー)供給体制構築が必要
エネルギー価格高騰は現時点でのエネルギー需給逼迫が原因であり、コロナ禍からの回復過程にある需要拡大に対し、供給が十分でないところに問題がある。
需給安定化のためには十分な供給を確保し、柔軟で強靱な供給体制を構築する必要がある。
産消対話など、国際協力促進も必要だ。
なるほど。
気候変動対策強化の副作用としてのグリーンインフレ?
そして、脱炭素化の影響が今後無視できないものになるリスクを掲げる。
脱炭素への移行期間においては、化石燃料は欠かせない。
よく聞く議論・主張だ。
脱炭素化に必要な再生可能エネルギーや電力化の促進に不可欠な希少鉱物などの価格高騰とそれに起因するエネルギーコスト上昇懸念。
これも同様。
そして最近頻繁に目にし、耳にするようになった、気候変動対策強化の副作用としての「グリーンインフレ」懸念。
さまざまな懸念材料・情報を取り出して、以下の結論に結びつける。

毎度のことながら、エコノミストやマスコミ専門家の役割とはなに?
日本も世界も脱炭素化への取り組み強化と同時に、エネルギー安定供給の双方にバランスよく目配りした政策・戦略が不可欠だ。
今回の価格高騰は社会がやはりエネルギーコスト上昇に敏感であることを改めて示した。脱炭素化に向けた過程でエネルギーコストが上昇する場合も、それを最小化するための英知・工夫が必要になる。
(エコノミスト360°視点)というコラムでの小論。
360°俯瞰すると、総合的に、俯瞰的に、このレベル、視点での主張・提案・内容に落ち着くということなんでしょう。
バランスよく目配りした政策・戦略とはいかなるものか。
脱炭素化の過程でのエネコスト上昇時の最小化するための英知・工夫とは、どうすれば集約できるのか。
そこを鋭くかつ穏やかに、実現可能な内容で、的確に提示できるのが、真のエコノミストと思うのですが。
そして究極の安定供給システム構築のためのエネルギー自給自足体制構想の長期ビジョン・戦略にも視点を当てるべきことも。
関連6記事を総合的に俯瞰すると???
1日に、エネルギー関連記事を、拾っただけでも6つも掲載した日経紙。
各記事情報を取材し、署名した記者諸兄は、それらを総合して評価し、俯瞰的に問題を整理し、政策提言に持ち込んでくれるのでしょうか。
情報収集と発信にいかにコストと能力を費やしているか、その価値に自信をもっている企業と諸兄ですが、過ぎていく時の中での価値は、具体的な提案・提言のアウトプットと政治・行政への影響力を持ち得てこそのもの。
そのくらいの基本認識は持って当然の人びとと、毎度のことと思うのであります。
今回は、6記事中、国内事情に焦点を当てた3記事となりました。
実は、昨年第4四半期以降、日経でチェックした、エネルギー関連記事が数多くあったのですが、他ジャンルの書籍を材料としてのシリーズ記事化に重きを置いたため、手つかずのままにしていました。
今回の投稿を機会に、遡って整理・チェックし、これはと思うものを、新たに掲載される記事も併せて、取り上げていきたいと考えています。

以下は、前回記事に投稿したものの再掲です。
2050年国土・資源政策長期ビジョン構築に向けて
こうした情報の確認等を通じて、当サイトが提案する以下の<国土・資源政策2050年ビジョン>における関係政策の一層の深化・具体化に結びつける予定です。
他の3つのジャンル、<社会政策 2050年ビジョン><経済政策 2050年ビジョン><国政政策 2050年ビジョン>と合わせて、宜しくお願いします。
Ⅰ 国土・資源政策 2050年長期ビジョン及び長期重点戦略課題
<2050年国土・資源政策長期ビジョン>
有限の国土及び各種資源の安全保障を守り、持続性を備えた可能な限りの自給自足国家を確立し、国民の命と安全・安心を守る国家政策の2050年の実現・追究を図ります。
<2050年国土・資源政策長期重点政治行政戦略課題>
1.国土安全保障・維持総合管理
2.電力・エネルギー安全保障・維持開発管理
3.食料、農・畜産・水産業安全保障安全保障・維持開発管理
4.自然環境保全・持続可能性管理
5.社会的インフラ安全保障・整備維持管理
6.産業資源安全保障基盤・維持開発管理
2.電力・エネルギー安全保障・維持開発管理
(基本方針)
気候温暖化・自然環境破壊などがもたらす国民生活、各種事業活動上の不安・悪影響を抑止し、将来に向けて持続可能な電力・エネルギー自給自足体制の整備、安心・安全を保障する同システムの構築を推進し、2050年までに100%再生可能エネルギー国家と水素社会を実現する。
(個別重点政策)
2-1 100%再生可能エネルギー及び水素社会の実現
1)各再生エネルギー別現状及び長期問題点・リスクなど調査及び分析( ~2030年 )
2)個人住宅及び事業所建物再生エネ発電・電源利用義務化及び支援法制化・施行(~2030年)
3)長期電源構成ビジョン及び長期計画策定(~2025年)、エネルギー危機管理システム策定 ( ~2030年)
進捗・評価管理 (2031年~) 、100%エネルギー自給自足国家化(~2050年)
4)水素エネルギー社会化技術開発調査及び長期計画・予算策定( ~2030年)
プロジェクト進捗・評価管理 (2031年~) 、(100%再生可能エネによる)水素社会実現( ~2050年)
2-2 電力送配電網の国有化と家庭用電力基本料金の無料化
1)現状電力送配電網問題点調査及び方針立案(~2025年)
2)送配電網国有化法制化及び予算化、移行・実行計画立案(~2030年)
3)電力会社等電力事業システム再構築(国・地方自治体・民間企業及び個人・一般企業)
4)家庭用電力料金無料化(2050年~)
2-3 GXグリーン・トランスフォーメーション推進、原子力発電の停廃止と完全安全技術転用
1)産業別・企業別GX推進計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
2)国家主導・支援GX推進計画・支援計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
(1)2)参考)
3)必要原子力発電関連技術活用政策、長期計画策定 (~2030年)
4)原発停止方針確定、福島原発処理他廃棄物処理長期計画策定・予算化 (~2030年)
4.自然環境保全・持続可能性管理
(基本方針)
有限の国土・自然環境のもと、環境保護・自然保全、観光・文化資源保全と有効活用などの政策を推進し、持続可能な仕組み創りを2050年までに実現する。
(個別重点政策)
4-1 カーボンゼロ政策推進
1)長期カーボンゼロ化計画策定 (~2025年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
2)炭素税法制化・運用管理化 (~2025年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
3)産業別・企業別カーボンゼロ化促進政策具体化 (~2030年) 、進捗評価管理 (2031年~)
4)環境・エネルギー政策との統整合
4-2 自然環境の保全・保護・持続性確保長期整備
1)自然環境実態調査 (~2025年)
2)モデル自然環境・森林海浜保全保護計画策定 (~2030年)
3)環境政策課題体系化・総合化・個別計画立案、長期取り組み計画策定(~2030年)
4)再生可能エネルギー活用自然等との調整 (~2030年)
4-3 観光・文化資源の維持、有効活用
1)観光・文化資源実態調査と保全方針・計画立案(国家レベル)
2)地域文化・伝統保全方針及び支援計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)
3)国内観光・文化資源評価と維持・活用方針 (~2030年)
4)インバウンド観光・文化資源評価と維持・活用方針 (~2030年)
コメント