介護保険制度「要介護認定」有効期間を延長へ
厚労省が、現状の介護保険制度における「要介護・要支援」のランクの認定の有効期間を、現状の最長36カ月から48カ月に延長することに。
その理由は、現状の認定の更新手続きを要する高齢者、その度合の区分変更の申請を行う高齢者、新規に要支援・要介護度の認定を申請する高齢者が増加する一方、そのときの面談と審査のもととなる調査書類を作成する「認定員」の人手不足にあるという。
しかし、元々、一度認定を受けた場合、より支援・介護を必要とする度合いに変化した場合を除けば、頻繁に更新のための申請や面接を行う必要がないのではと思うのだが・・・。
一旦なにかしらの認定を受けている人は、介護の必要性が増した場合にのみ、区分変更の申請を行うという方式でよいのではと考える。
言うならば、要支援・要介護区分変更は「申請方式」にというものだ。
但し、この申請者は、介護などを受ける本人の希望の有無を問わず、「ケアマネジャー」の職務とすることを提案したい。
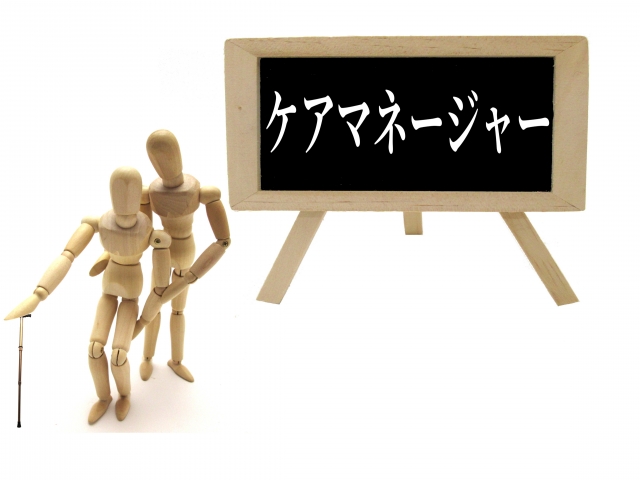
自身の義母の介護度変化の推移と経験から
2015年12月、94歳だった義母が大腿骨を骨折し、手術とリハビリ後、サ高住に入所。
初めての認定申請を行ったその時の結果は「要介護1」。
一年後の更新時の認定もそのままの「要介護1」。
2回目の更新時には、改善が見られたということで「要支援1」に変更。
3回目の定期の更新時には、「要介護1」と元に戻った変更。
その時に初めて、有効期限が2年とされた。
そういう制度になっていたことは、新しい介護保険証を受け取って初めて知った次第。
そして、まもなく2年を経過して、定期の更新時期の1月を迎えようとした直前の昨年11月に再度大腿骨を骨折。
98歳の超高齢ということもあり、再手術は行わないことに。
当然身体の機能に大幅な低下がみられ、区分変更の申請を行い、12月に面接・審査。
その結果、再度の骨折前は歩行器での移動が可能だったものが、完全に「車椅子」生活に。
「要介護4」と、生活全般に介助を必要とする重度の区分に変更された。
なお、12月に行った区分変更申請は、施設と後見人である私とケアマネジャー3者で相談し、義母の名前で行ったが、申請書類作成と提出は、ケアマネジャーが代行してくださった。

要支援・要介護認定更新は、原則、区分変更申請時のみに変更を!
厚労省によると、直近の要介護認定から48カ月・4年後においても前回と変わらなかった人の割合は33.4%が変化なしとのこと。
当然、2年後・3年後ではより変化がないはず。
やはり、区分変更を必要とする場合のみ、自治体の介護部門に申請をすれば、相当の負担の軽減になるに違いない。
介護施設や介護スタッフの事業収益面からの申請に任せると問題があるだろうから、毎月のケアプランを作成し、介助の必要性などにつき的確に把握しているいるケアマネジャーが、施設または本人からの申し出に基づき実情を把握した上で、申請する方式が望ましいだろう。
要支援・要介護度が、施設サイド(及び本人)の努力により軽度に改善された場合の区分変更の申請も、同様の方式にすれば問題ないだろう。
申請主義とは言っても、一応の有効期限は設定し、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証等に表示しておくべきだろうから、今回の改訂で考えている48カ月・4年間とし、その期限後も変更を必要としない場合は、延長申請をすれば、面接なしで4年間更新され、新しい介護保険証を交付することにすればよい。
もちろん、要介護度の基準や適用範囲などの改訂が行われれば、そうはいかないが・・・。
まあ、こうした事務手続き的なフローについては、まだまだ他にも改善可能な部分があるのでは、と思う。
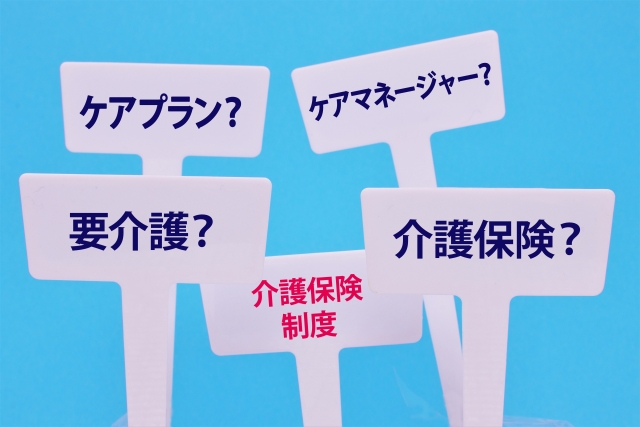
コメント