2021/12/12付日経で
「DXが経常黒字を下押し クラウドに支払い、赤字1兆円超」
と題した記事をみた。
こういう書き出しだった。
官民あげて取り組むデジタルトランスフォーメーション(DX)が経常黒字を縮小させている。米IT(情報技術)大手が強いクラウドサービスなどの海外への支払い超過が1~10月に1.1兆円を突破(1兆1894億円)した。DX加速は待ったなしだが、中長期的には基幹システムを海外に頼らざるを得ない国内産業の弱さをどう克服するかも課題となる。
その額は、同期間の貿易黒字2兆5198億円の5割近くに当り、クラウドサービスの利用料の支払いが多くを占めているのではないかとされる。
クラウドサービスとは
クラウドサービスとは、離れた場所で動くコンピューターを、インターネットを介して使うサービス。
よく耳にし、目にする「クラウド」は、「クラウド・コンピューティング」のこと。
そのクラウド・コンピューティングを利用したサービスが、「クラウド」または「クラウドサービス」である。

米国御三家に圧倒されるDX、ITインフラ、プラットフォームとしての「クラウドサービス」
クラウドと聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、やはり、 Amazon(AWS)、MS、Google の御三家。
基盤システムをクラウド上で提供するPaaS型サービスのシェアは、それぞれ、37.4%、30.6%、15.9%と圧倒的。
昨年デジタル庁を創設し、まさに国を挙げてのDXのはずだが、この状況はなんともお寒い限りだ。
一生懸命取り組もうとしている経済安全保障からも、IT、デジタルに絡むインフラは、自国で供給し管理すべきことは言うまでもない。
政府も一応「国産クラウド」の活用を模索したらしいが、総務省は昨年2月AWS(アマゾン・ウェブ・サービス)、肝心要のデジタル庁は今年10月、行政システムのクラウド化に使うサービスにおいてAWSとグーグルの2社を選んだという。
要は現状の日本のクラウドサービスは、個別各社のニーズへの対応が得意であり主で、いわゆるプラットフォームビジネスでは、先の米国御三家に圧倒されているわけだ。
このビジネスの在り方・特徴をベンダーロックインと言うそうだが、言うならばこれによりロックインされ、身動きがとれない状態に陥り、特徴が弱みになっているというわけだ。
日本のこうした状況については、以下の記事が参考になる。
⇒ クラウドサービスとは?「クラウド」を具体的にイメージしてクラウドサービスのメリット・デメリットやその種類についても理解しよう!|サービス|法人のお客さま|NTT東日本 (ntt-east.co.jp)
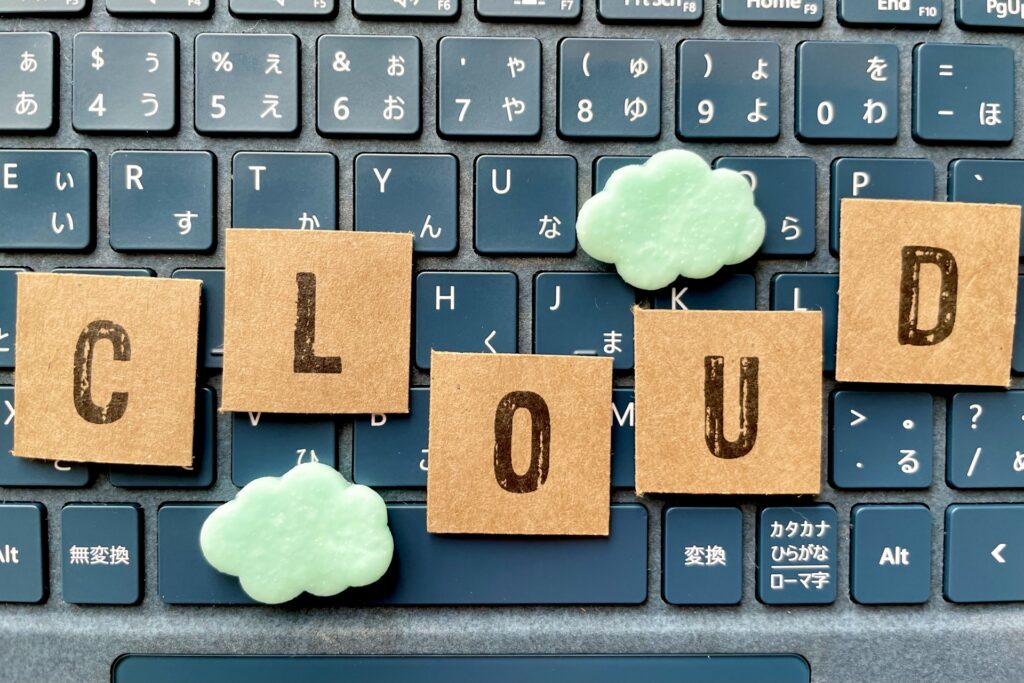
経済安保からも必要なクラウドサービスの自国サービス化
日経記事は、こうまとめている。
足元で必要なのはDXの加速であり、グローバルに汎用性のある米ITのサービス活用は不可欠だが、中長期的には海外に拡販できるようなデジタルサービスを日本でどう生み出せるようにするかが課題になる。
技術革新の停滞を打破する構造改革が求められる。
構造改革という言葉を用いることが適切とは思わないが、要は、今後もクラウドサービスのニーズは、国内に限っても拡大し続けることは間違いないはず。
であるならば、そのための供給体制の整備・拡充を、半導体事業と並んで、国家プロジェクトとして、産官学共同で進めることが望ましいと思う。
もちろんそのニーズは、需給対応という経済対策と安全保障面からのアプローチにあるだけではない。
情報セキュリティとこれに繋がる日本という国家の安全保障政策としてのニーズからも不可欠な課題である。
サーバーが自国外に設置されることに伴う根本的かつ致命的なリスクに対する対策としても、クラウドサービスの内製化は必須となる。
この課題については、先に投稿済み記事
◆ ビル・ゲイツもスティーブ・ジョブスも自分の子どもにはスマホもタブレットも持たせなかった:堤未果氏著『デジタル・ファシズム』から(2021/12/6)
で紹介した、 堤未果氏著『デジタル・ファシズム 日本の資産と主権が消える』(2021/8/30刊・NHK出版新書) を用いてのシリーズの第1回目に予定している<第1部 政府が狙われる>編で、本稿を受けて取り上げることにしたい。
(参考)第Ⅰ部 政府が狙われる
第1章 最高権力と利権の館「デジタル庁」
第2章 スーパーシティの主権は誰に?
第3章 デジタル政府に必要なたった一つのこと

コメント