昨日2月9日日経1面に、2つの半導体関連記事が載った。
◆ TSMC、日本に拠点 先端半導体開発で連携へ
◆ ルネサス、英半導体ダイアログを買収 6100億円で合意
(一応、記事へのリンクを貼ってありますが、一部しか見れないかもしれません。)
前者の、TSMCとは、コロナで世界的に供給が逼迫している半導体の台湾のメーカー。
欧・米・日からのTSMC詣でが報じられるなかでの今回の報道。
本音では、日本の半導体メーカーの存在感のないことが歯がゆいところだが、今後の展開を考えると、中・韓のシェアの拡大抑止対策をも含めて、これを機に、国内戦略を再構築してほしいと思う。
後者は、国内半導体大手のルネサスエレクトロニクスによる、同業、英ダイアログ・セミコンダクターの6179億円での大型買収発表報道。
関連の技術を持つ。主力は自動車向けだが、成長が見込める高速通信規格「5G」分野関連技術を取り込むことを目的としているもの。
買収後のマネジメントが最大の不安だが、国内体制の基盤強化と拡大に繋がるものであってほしい。
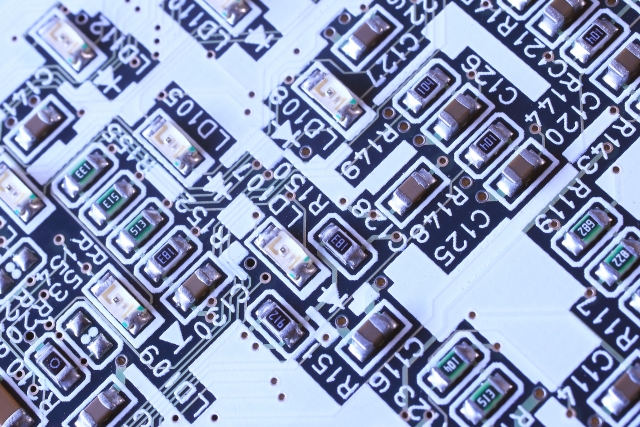
2050年に向け、各分野で自給自足可能な社会経済システム構築を
かねてから、コロナを教訓として、日本、日本人、日本企業の社会経済システムにおいて、できる限りの分野での自給自足体制・システムを構築すべきと考えてきている。
そろそろというか、早くもというか、早期退陣が予想されている菅内閣において唯一評価できると考えている「ゼロカーボン」への移行政策。
これは、究極的には、再生可能エネルギーによる100%エネルギー自給自足国家作り戦略を推進することと読み替えるべきと考えています。
首相や官邸・官僚にはそこまでの発想・構想力・想像力はないようですが。
今回の半導体報道で感じたのは、やはり、産業の米と称される半導体も、基本的には自国内で供給できる体制を構築すべきと常に考えてのことです。

産業の米、半導体の国内ニーズは、増えることはあっても減ることはない
コスト及びその競争力を考えると、すでにタイミングを逸したと考える専門家や経営者はいるだろう。
かつて国内産業化に進んだ時期もあったが、結局多くは失敗し、撤退し、今の中・台・韓(サムソン)のグローバル・チェーンの構築とシェア分配体制を手をこまねいて許すことになってしまった。
しかし、今回の台湾TSMCの日本への進出、拠点化は、今後の見通しに基づくものである。
できうるなら、新会社は、日本企業が加わっての合弁であってほしい。
本音をいうと、国内の大手複数企業が出資し、政府も補助金を出して、純粋な半導体日本企業を創設すべきと思います。
しかし、スピードを重視するならば、今回のTSMCの進出は願ってもないことである。
但し、やはり合弁会社が望ましい。
日の丸半導体企業であるルネサスもなんとか生きながらえつつ頑張ってはいる。
その結果としての英国企業買収なのだろうが、先述した大手企業の出資による戦略的企業の軸になってもよいのではとも思う。
ただ問題は、価格。
既に、ある意味、世界的なシェア、企業力ランキングでは態勢が決している感がある半導体分野の中で、国内需要を満たす規模で経営が可能かどうか。
一つの裏付けとして、半導体を必要とする全産業分野(農業も含む)と政府・官庁・地方自治体、保育・教育・介護、医療・保健、住宅・都市開発等の公共的事業領域すべてで、5年、10年単位で、2050年までの需要予測を立ててみてはどうかと。

長期ビジョン構築と長期プロジェクトマネジメントの必要性
しかし、こうしたプロジェクト・マネジメントができる政治家は皆無であろう。
本来、そのために優秀なはずの官僚もいるのだが、誰も10年、20年、30年先を想定・設定したプロジェクトなど経験したことがないし、やる気がない。
ジョブ型が叫ばれるのだが、メンバーシップ型官僚がほとんどだろうし。
とすると民間企業か研究者に人材を求めることになるだろうか。
しかし、そんな発想はあるまい。
みすみす既得権を手放すわけもないし。
いずれにしても、国家としてこういう長期ビジョン・構想と、長期にわたる、世代を継承していく、今の時代で言うところの「持続(可能)性」を前提・条件とした社会システム、社会経済システム構築プロジェクトが必要であろう。
選挙のことや、いつになったら大臣になれるか、のレベルの発想と行動しかとれない政治家と政党。
やはり、政治改革が優先しないと、始まらない、という思いがついつい湧いてきてしまうのが残念です。
コロナが、我々に学ぶことを強制しているこれからの持続可能な社会のあり方。
その中で、経済に焦点を当てて、「長期社会経済システム構築」シリーズ的に課題提起していければと思っているます。
なお、経済への着眼ではなく、人間系の社会システムの変革・構築という視点での「長期社会システム構築」シリーズも、と考えています。

コメント