以前から気にはなっている人物に落合陽一氏がいる。
誰かとの対談形式での新書が昨年出たと思うが、入手する機会を得ぬまま、忘れてしまい、今年に入っていた。
しかし、先日、単独執筆での『働き方5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ』という新書が出たのを知り、6月6日にネットで発注して入手。
他に読む予定だった種々の新書に一区切りついたので、3日前に手にし、昨日斜め読みを終えた。
(読んで、これより先2016年に『これからの世界をつくる仲間たちへ』が発行されており、その新書化だと知った。どの程度手を加えているのかは、いずれ確認したいが。)
落合陽一は、GIFT だ!
読み進めるうちに、彼は、天才なのだが、そう呼ぶのはどうにも今の時代にも、これからの時代にもそぐわない。
思った!
彼は、必然的に地球に舞い降りた、あるいは宇宙のどこかから地球に遣わされた、GIFT なのだ、と。
日本語にする必要はない。
否、してはいけない。
彼自身が、GIFT そのものなのだが、別の面から見ると、あるいは考えると、地球が、社会が、そして我々が受け取った、GIFT なのだ。
本人にその意志、気持ちがなくとも。
『これからの世界をつくる仲間たちへ』とタイトルに添えられているように、コンピュータおよびAIが、自然なこととして、仕事にも生活にも既に組み入れてしまっている(であろう)若者や彼の同世代へのメッセージ書である。
人間がシステムの下請けになるAI時代。
またこういう表現もなるほどと思わせる。
人間がAI のインターフェイスになる。
(もう既になっていることをなるほどと思わせる例も提示している。)
そして、研究にあたって、次の5つを自問自答するよう提案している。
なるほど、という感じだ。
1.それによって誰が幸せになるのか。
2.なぜいま、その問題なのか。なぜ先人たちはそれができなかったのか。
3.過去の何を受け継いでそのアイディアに到達したのか。
4.どこに行けばそれができるのか。
5.実現のためのスキルはほかの人が到達しにくいものか。

「ワーク・ライフ・バランス」ではなく「ワーク・アズ・ライフ」
自由な時間を手に入れるために働くということは、「ワーク・ライフ・バランス」を考えることに繋がる。
時間を切り売りして稼ぎ、その稼ぎで、遊ぶ、旅行するなど、すなわち消費するために自由時間を使うことになるからだ。
だが、これからの望ましい働き方は、「ワーク・アズ・ライフ」。
ワークとライフを区別せずに、自分のやりたいことに時間を使う生き方、と彼は言う。
私の場合、ちょっとニュアンスは違うが、1988年に独立して経営コンサルタントとしての仕事は、好きでやっていることで、趣味は仕事、という感覚でやってきた。
年金ぐらしになった今は、収入が入る仕事はないが、このサイトを日々運営する生活を、好きでやっている。
世代継承のつもりで、何かしらの夢・目標を持って。
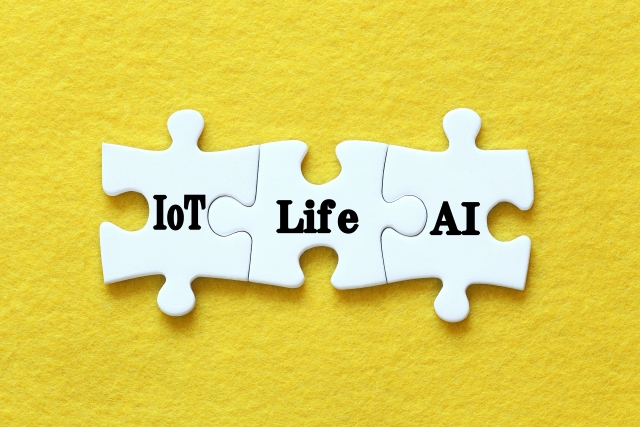
AI で、どこまで社会改革を実現できるか
彼が望ましいとする、そして若者が目標とすべきとする「クリエイティブ・クラス」になることも、「デジタルネイチャー」として社会に身を置くことも、どうあがいても不可能な「逃げ切り(はしないぞ)世代」。
ではあるが、社会を変えなければいけないという強い思いはある。
というか、日々一層強くなる。
そこで、AI は、彼も必要と認識している社会変革を可能にするのか?
私がAI に期待するのは、1点そこにある。
残念だが、駆け足で1回読んだ限りでは、その明確な方法を、書からは検索できなかった。
しかし、ヒントや刺激は得た。

AI とベーシック・インカム
ところで、この書の中で1か所だけ、当サイトの主テーマになってきた「ベーシック・インカム」という用語が出てくる。
「コロナ危機によりスペインでベーシックインカムの支給が宣言された時期がありましたが、デジタル化に伴う社会改制度の変革はこういった危機の時にあきらかになります。」
という件だ。
AI社会の出現がもたらす脱労働社会においては、ベーシック・インカム制度の導入が望ましいという提起は、先に
◆ ベーシック・インカムとは-3:AIによる脱労働社会論から学ぶベーシック・インカム
において取り上げた、井上智洋氏著の『AI時代の新・ベーシックインカム論 』
で確認した。
やはり、当書の前に同氏は、『人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊 』(2016年7月初版)を送り出している。
AI 社会が、社会改革を引き起こし、そこでベーシック・インカムが有効になり、それがまた新たな社会改革を促す。
そういう望ましい循環のみをAIはもたらすのか。
そういう楽観論とは、今ところ、落合氏と井上氏の書では断定できないと思う。
ネットやAIの悪用が拡大を続けている現状があるからだ。
もう一度、彼らの書や考え方を確認する必要があるとは感じている。
AI社会とBI ベーシック・インカムの結びつきは、一つの局面によるきっかけ・要因・誘引レベルのことであって、人間社会における必然的なニーズによるもの。
そう考えた方が適切ではないかと考える。
しかし、AI社会の出現・進化・深耕が、その要求・要請を一層強く促すなら、またその合理性を一層強化するならば、その機会は逃さないようにすべきだろう。
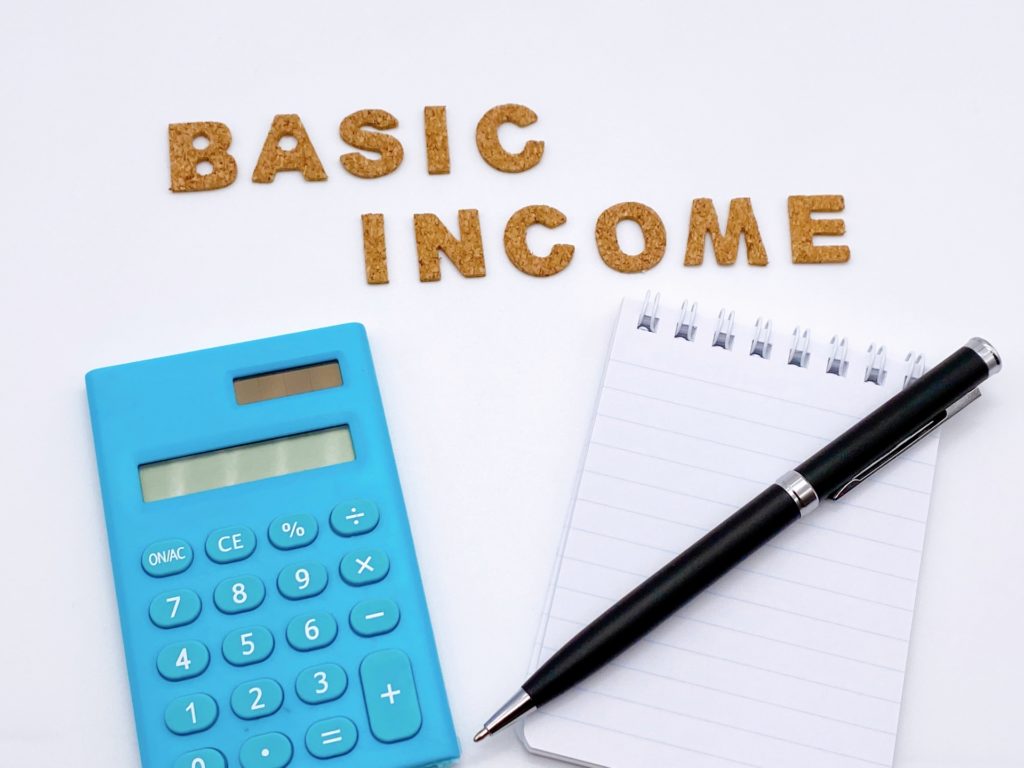
働き方5.0と2050SOCIETY はどう繋がるか
そういう意味で、働き方5.0が、当サイト ” 望ましい2050年の社会 “ の実現と結びつくならば、より望ましいことと思う。
働き方5.0とは、
・狩猟社会 1.0
・農耕社会 2.0
・工業社会 3.0
・情報社会 4.0
に続く、新たな社会の姿。
AIやロボットが端広い分野で進化し、人間とともに働いていく時代の
・働き方社会 5.0
と彼は位置づけたもの
・働き方SOCIETY 5.0
とも言える。
ヒントや知っておくべき用語が多々あった書。
働き方イコール生き方と考えるゆえに、働き方5.0は生き方5.0と読むこともできる。
当サイト https://2050society.com が求めていく2050年の望ましい社会は、働き方5.0によるSOCIETY 5.0とどう繋がっていくか、どう繋ぐことができるか。
落合氏は、ここ数年、身体障害者や高齢者の補助や介助などのプロジェクトにも特に取り組んでいるという。
例えば具体的には、自動運転車椅子を開発。
介護士の手間を削減するための研究開発として、VRのヘッドセットとコントローラーを使って車椅子を遠隔操作したり、隊列走行させるなどのプロトタイプを作っている。
これなどは、このサイトのテーマカテゴリーの一つである介護と関連している。
ただ、そのアプローチには、正直特に目新しさは感じない。
なぜならば、その取組みは、身体的・物理的な技術開発に主眼を置き、介護制度や介護行政という社会システムの改革・変革とは直接結びつかないからである。
介護する人・介護される人のマインドの領域に、AIが、コンピュータがどこまでアプローチできるか、心にタッチできるか。
あるいはどこまでタッチすべきか。
彼いわく、AI が持つことができない、人のみが持ちうる「モティベーション」そのものの形成に、どこまでAI が寄与できるか。
結局は、彼も言っているように「世界は人間が回している」ゆえに、AI が、社会を変革する人間を輩出するように持ち込むことが、働き方5.0で果たして可能になるかどうか。
それが、クリエイティブ・クラスやデジタルネイチャーの誕生を待たなければ不可能ならば・・・。
同氏やAIへの語りかけが、延々と必要になるのでは・・・。
そんな気もするのだが。
継続していくことにしよう。
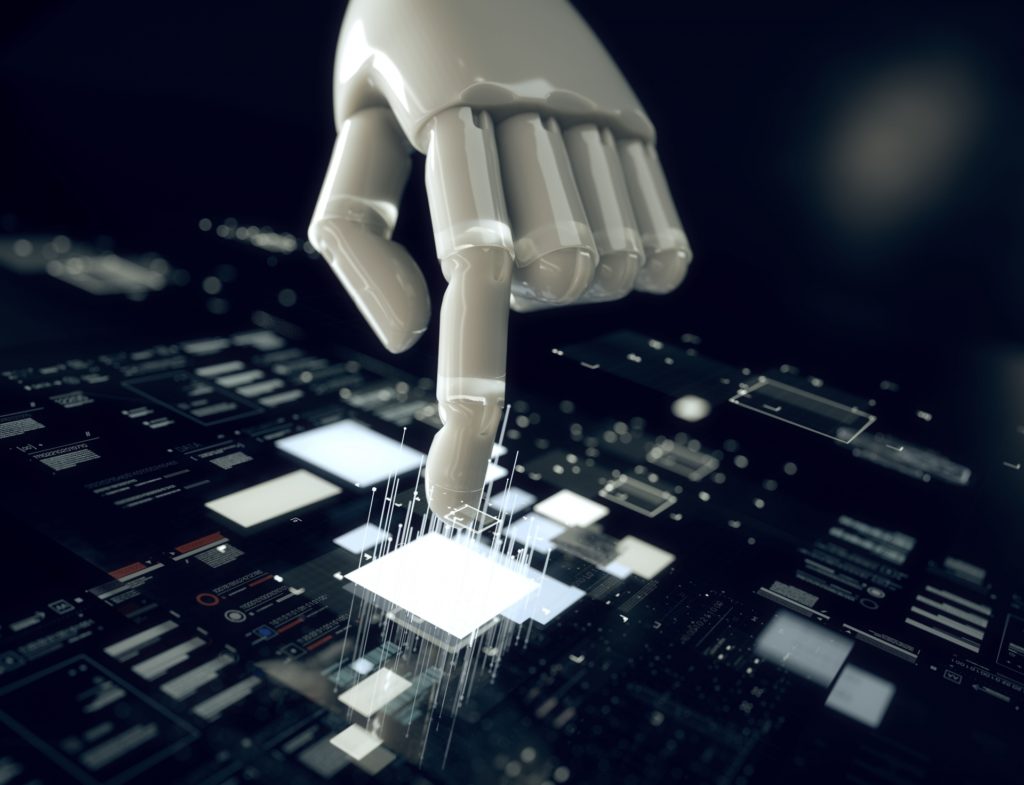
読みやすく、分かりやすい書。全世代、是非一読を
内容はもちろんだが、実は最も感心したのが、読みやすく、分かりやすく書かれていたこと。
このところ手にしている新書の多くが、大学に身を置く人の書。
データがどう、エビデンスがどうというこだわりが強く、かつ学術的表現なので、一度読むだけではすんなり頭が受け付けてくれない。
それに対しての本書には、親しみを感じる。
AI書でありながら、人間味を感じさせるのだ。
デジタル・ネイチャーとしての人間味、とでも言うべきか。
現役世代はもちろん、若くはない世代のあなたも、そしてあなたの子どもにも、孫にも読んでもらいたい書。
値段もお手頃の『働き方5.0 これからの世界をつくる仲間たちへ』。
私にとっての今年上半期のベストの新書。
お薦めします。
コメント