新書の表紙カバーについている帯に” 8050問題に発展させないため「放置」せず「行動」を ” とあったので、興味深く読み始めた
『不登校・ひきこもりの9割は治せる 1万人を立ち直らせてきた3つのステップ 』(杉浦孝宣氏著・2019年初版)。
ですが、序文に当たる部分で、「20歳くらいまでの間ならば」という条件がついていることを知り、ちょっぴり残念に。
以前に、
『8050問題の深層: 「限界家族」をどう救うか 』(川北稔氏著・2019年8月初版)
『中高年ひきこもり』(斎藤環氏著・2020年1月初版)
を読み、中高年のひきこもり対策の方を先に取り上げたいと思っていたので。
20歳未満ならば、8050問題は、先の先。
30年以上も後のことなので、優先としては、すでに中高年に至っている人、あるいはその直前にあり、もうすぐそうなるリスクを抱える人についてテーマにしようと思っていた次第。
しかし、加えてそこには、
「20歳以降の大人になり、ひきこもりが長期化すればするほど、社会復帰への道は険しくなる。」
「長期化を予防するためにも、20歳前までの今この時期が大事。」
とあった。
いじめ問題と不登校・ひきこもり問題を結びつけ、そこでの教育のあり方を絡めて考えていきたいとかねてから思っていた私。
教育に関しては、もうすぐ
『教育は何を評価してきたのか 』(本田由紀氏著・2020年初版)
を読み終えるので、その後の課題にという予定だった。
しかし、杉浦氏の実体験に基づく本書は、説得力があり、今回紹介だけでもと思い、本当にエッセンス部分だけを取り上げることにした。
関心をお持ちの場合、ぜひ詳細を、同書で確認頂ければと思います。
不登校の定義と実態
文科省の定義によると、不登校とは
「年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童生徒」のうち「何らかの心理的、情緒的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的理由」による者を除く)」。
そして、2017年度では、中学生は31人に1人、小学生は185人に1人いるという。
中学校では、クラスに1人はいることになり、身近な問題になっていることがわかる。
また、クラスで目立つ生徒、積極的な生徒、勉強ができる生徒でも、不登校になるケースが少なくなく、このところその数は増え続けているデータが示されている。
ひきこもりの定義と実態
一方厚労省の定義では、ひきこもりとは
「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けてひきこもっている状態」。
その世帯数は約32万世帯、2015年では、15歳~39歳で54万1千人、2018年で40~64歳で61万3千人、合計では100万人以上いると推計されている。
すなわち、ひきこもりの長期化と高齢化が問題の大きさと深さを示す状態になっている。

ひきこもりになる4度のタイミングとは
本書では、ひきこもりになりやすいタイミングは人生で、次の4度あるとしている。
1.中1ギャップ
2.高1クライシス
3.高校卒業直後
4.就活での失敗
<中1ギャップ>は、中学入学時における、入学・転編入学・進級時の不適応、部活などへの不適応、学業不振等によるもの。
<高1クライシス>は、留年・退学がある高校へのシステムの変化に起因するもの。
<高卒直後>は、浪人中に因する場合と大学入学後の目標ロス等。
<就活の失敗>は文字通りのこと。
これは、あくまでも20歳前後までの人生を想定してのこととであろう。
中高年のひきこもりでは、もちろん、若い世代でのそれらの機会に因する場合もあるだろうが、その後の社会人生活おける、職場でのパワハラや人間関係などを原因とする要因が多くを占める。

不登校を生む教育現場の課題と不登校対策の有効な受け皿
また、不登校を発生させやすい学校現場の特性として、以下の事情を例示しているが、詳細は割愛したい。
1.私立高・女子高の不登校対応の弱さ
2.スポーツ推薦入学時の退部の退学への結びつきやすさ
3.スクールカウンセラーへの過剰な期待
4.適応指導教室の使いにくさ
5.性的マイノリティへの配慮不足
なお、そうした要因で不登校が発生した場合、その対策を講じる上で、次の条件が確保されていることが、有効としている。
これについても、詳細は同書で確認頂ければと思う。
1.通信制高校がある。
2.サポート校が存在。
3.保護者同士で話せる場があり、利用できる。

子どもに対する親のあり方・関わり方3か条
不登校やひきこもりの改善・解決には当然、子の親ががどう関わるかが課題となる。
筆者は親のあり方・関わり方として、以下の3か条が不可欠とする。
これは、しっかり抑えておく必要がある。
1.親(特に父親)が本気で向き合う
2.無条件の愛情で接する
3.甘い対応はしない
こうした決意を持った上で、スタッフと本人と意思統一・意思疎通を測って実際の克服過程に入っていくことになる。
その過程は、3つのステップを順に進めていくのだが、それぞれのステップにおける手順を次に引用した。
不登校・ひきこもり克服の3つのステップと主な体験手順
<ステップ1.規則正しい生活をする>
・高校生インターンスタッフによる訪問(初めはベテランスタッフと組んで)
・身支度を整える(お風呂・歯磨き・ヘアカット等)
・連れ出し(週1回でも家から出る)
・大人とコミュニケーションをとる
(今後の通学先となる場所の大人との信頼関係を築く)
・規則正しい生活
<ステップ2.自律して自身をつける>
・同世代と交流する(行事やイベントへ参加)
・みんなの役に立つ仕事をする
(行事やイベントの企画運営、委員会や係、生徒会等)
・進路について考える
(親とスタッフの三者で本人が本当に望む進路を考え、そのための勉強をしていく)
<ステップ3.社会貢献をする>(支援する人から支援する人としての経験)
(例)・学生インターンとして活動
・生活改善合宿体験
・障害のある人とのコミュニケーションや体験

病気との関連、その考え方。スマホ・ゲーム依存対策
乱暴な処理の仕方で本書のポイントを紹介してきたが、私が特に共感したのは、
近年、「起立性調節障害」「発達障害」「うつ病」などと診断され、それが原因で不登校になったという相談が多いことを述べ、それぞれの症状なども紹介しながら、筆者がこう述べている点だ。
「そういった傾向があると軽く留意しながら指導するだけで、特別視することはなく、ひとつのパーソナリティ、個性としてとらえて普通に接している。」
「問題なのは、不登校になったり退学・転学などの手続きが必要になると、学校が医師の診断書の提出を求め、親がやむなく心療内科に連れて行く。すると、うつ病、不安障害、適応障害、統合失調症、自律神経失調症などの病気と診断されてしまう。」
「そこから、さまざまな向精神薬が処方され、どんどん薬が増え、向精神薬多剤投与という社会問題を引き起こすまでになっている。」
これは、不登校・ひきこもり児童生徒に対する問題だけでなく、現代に深く根ざし、広く拡散している問題と考えてよいだろう。
社会全体が神経症状に罹っているかのような時代感覚。
心療内科全盛になりつつある時代と社会に一抹以上の不安を感じている。
化合物薬剤が、心身の機能を麻痺させることができても、人間の心に優しく働きかける機能を持つとは考えられないのだ。
なお、筆者はゲーム・スマホへの過度な依存には配慮が必要だが、目の敵にするまでのことはないと言っている。
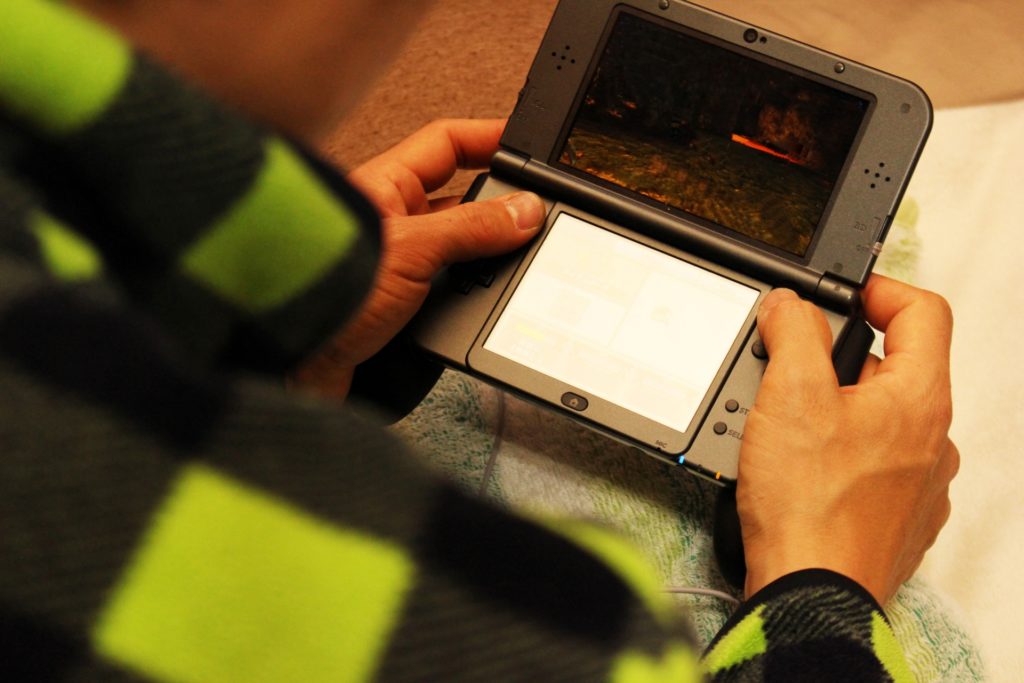
読後の想い
30年間この道一筋に活動してきた杉浦氏の実体験に裏付けされた話満載の書。
素晴らしいと思うが、問題は、そこで紹介されている諸条件を、どこでも用意・再現できるものではないということを確認しておく必要はある。
この方法を、今後、より広げていくためには、通信制高校やそのサポート校、プロの領域に達している専門スタッフ、合宿施設や就労体験を支援してくれる事業所・ボランティア・NPO法人、そして自身が不登校経験を持つ同世代インターンなど、同様のサポート体制を整備・構築する必要がある。
これは一朝一夕で済むことではない。
何よりも、関わってくれる人たちの辛抱強く、心底優しく深い愛情なくしてできることではない。
そして、この困難な事業を、民間だけに委ねてよいものか。
また、こうした問題が起きないような取り組み、いじめや教育現場で日常的におきている矛盾や問題行動への対策こそ先行して行われるべきではないか。
いじめ、種々のハラスメントのない学校・企業・社会にするにはどうすればよいか。
思いが尽きることはないが、まずは、お子さんの不登校・ひきこもりにお悩みの親御さんが、本書を手に取り、ご自分の家族・家庭で、今なにができるか、どんな選択肢があるかを考えるヒントを探して頂きたいと思います。
そして、可能でしたら、242ページにあるQRコードから、杉浦氏にご相談なさることをお薦めします。
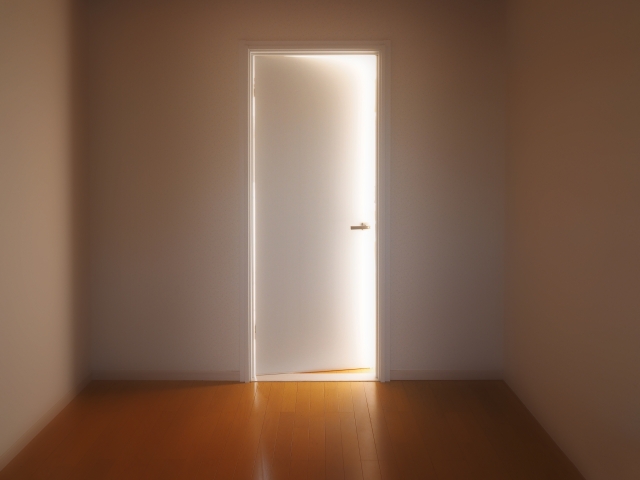
コメント